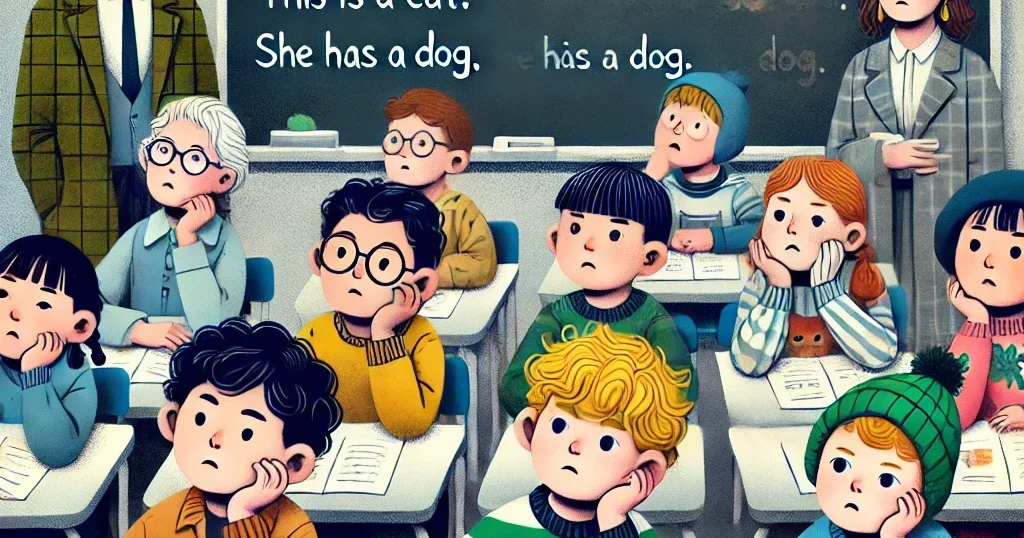突然ですが、「小学校の英語教育」って、どんなイメージがありますか?
「楽しそう!」「国際的でいいな」…そんなポジティブなイメージを持つ一方で、「ウチの子、大丈夫かな…」「英語嫌いになったらどうしよう…」と不安を感じている保護者の方もいるかもしれません。
実は今、小学生の間で「英語格差」と「英語嫌い」が深刻化しているという声が上がっています。
今日は、そんな小学校英語教育の現状と、その背景にある問題、そして私たち大学生や社会人が未来のためにできることを、一緒に考えていきましょう!
Contents
現場からのSOS!小学生の英語事情、ココが変わった!

2020年度から、小学校での英語教育が大きく変わりました。
- 小学3・4年生: 「外国語活動」として、英語に親しむ活動がスタート。(週1コマ程度)
- 小学5・6年生: 「外国語」が正式な教科に!成績もつくようになりました。(週2コマ程度)
このように「読む」「書く」だけでなく、「聞く」「話す」力も重視されるようになり、より実践的な英語力が求められるようになったんですね。
なぜ格差が生まれる?「できる子」と「できない子」の分かれ道

文部科学省の調査(※1)によると、小学校の英語教育について、
約7割の児童が「英語が好き」「どちらかといえば好き」 と回答。
一方で、約3割の児童が「英語が嫌い」「どちらかといえば嫌い」 と回答しています。
さらに、英語の習熟度には、家庭環境や地域による差が大きいという指摘も…!
一体、何が格差を生んでいるのでしょうか?
- 家庭学習の差:
- 英語の絵本を読んだり、英語の歌を聴いたりする機会が多い家庭の子どもは、英語に親しみやすい傾向があります。
- 保護者が英語に苦手意識を持っていると、子どもも英語を敬遠しがちになることも…。
- 塾や習い事の差:
- 早期から英語教室に通っている子どもは、当然ながら英語力が高くなります。
- 経済的な理由で塾に通えない子どもとの間に、格差が生まれてしまうケースも。
- 学校の先生のスキル差:
- 英語教育の専門知識や指導経験が豊富な先生と、そうでない先生とでは、授業の質に差が出てしまうことがあります。
- 特に地方では、英語の先生不足が深刻な地域も…。
- ICT環境の差:
- オンライン英会話や英語学習アプリなど、ICTを活用した学習機会の差も、格差を広げる要因の一つです。
- 家庭のインターネット環境や、学校のICT設備の充実度によって、学習効果に差が出てしまいます。
「英語嫌い」は、こうして生まれる…!
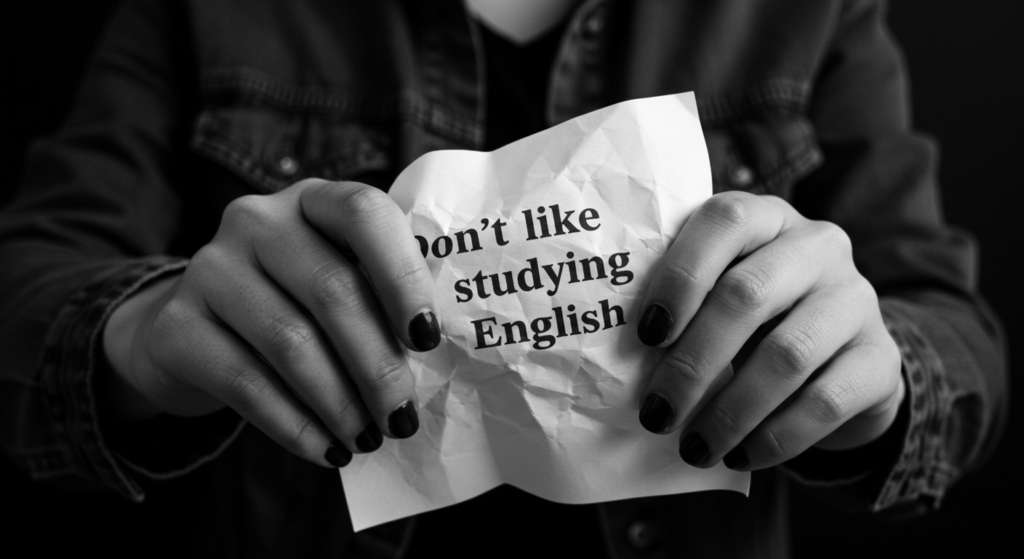
「英語が嫌い」になってしまう原因は、さまざまですが、主な要因としては…
- 「わからない」が積み重なる: 授業についていけず、「わからない」ことが増えると、英語に対する苦手意識が強くなってしまいます。
- 「失敗」が怖い: 発音を間違えたり、テストで悪い点を取ったりすると、「自分は英語ができない」と思い込んでしまうことも。
- 「楽しくない」と感じる: 単語や文法の暗記ばかりで、英語の楽しさを感じられないと、学習意欲が低下してしまいます。
大丈夫!未来は変えられる!私たちにできること

小学生の「英語格差」や「英語嫌い」…なんだか暗い話ばかりになってしまいましたが、諦めるのはまだ早い!
私たち大学生や社会人が、未来のためにできることはたくさんあります。
- ボランティア活動に参加する:
- 地域の小学校で、英語の学習サポートをしてみませんか?
- 子どもたちに英語の楽しさを伝える、貴重な経験になりますよ!
- 英語学習の情報を発信する:
- SNSやブログで、おすすめの英語学習アプリや教材を紹介してみましょう。
- 英語学習のコツや、モチベーション維持の方法をシェアするのもいいですね!
- 英語を使う楽しさを伝える:
- 海外旅行の経験談や、英語を使った仕事の面白さを、子どもたちに話してみましょう。
- 英語を学ぶことで、世界が広がることを伝えてあげてください。
- 教育格差の問題に関心を持つ:
- 英語教育だけでなく、教育格差全体の問題に関心を持ち、自分にできることを考えてみましょう。
- 署名活動に参加したり、寄付をしたりすることも、社会を変える一歩になります。
最後に…
小学校の英語教育は、まだ始まったばかり。課題は山積みですが、未来を担う子どもたちのために、私たち大人ができることはたくさんあります。
英語格差や英語嫌いをなくし、すべての子どもたちが英語を楽しく学べる社会を、一緒に作っていきましょう!
(※1)文部科学省「令和3年度 英語教育実施状況調査」
※上記は令和3年のデータですが、大幅な変更がない前提で執筆いたしました。最新の調査結果については文部科学省のウェブサイトで確認できます。
いかがでしたでしょうか。
少しでも、小学校の英語教育の現状と課題について、理解を深めていただけたら嬉しいです。