今回はTOEICの特徴を説明していこうと思います。
ここではあくまでの「TOEICって何?」って方々の為に情報を凝縮したものを提供いたしますので、5分位で読めると思います。
主なTOEICの特徴は以下となります。
【TOEIC】 ・出題形式が主にビジネスシーンを想定されたものが多い ・基本的にはリスニングとリーディングのテストである ・試験結果が合否ではなくスコア(得点)で表される ・スピードが求められる、試験の回数が多く試験会場も多い ・連続で受験した方がスコアUPしやすい
それぞれ説明していきます。
Contents
基本的にはリスニングとリーディングのテストである

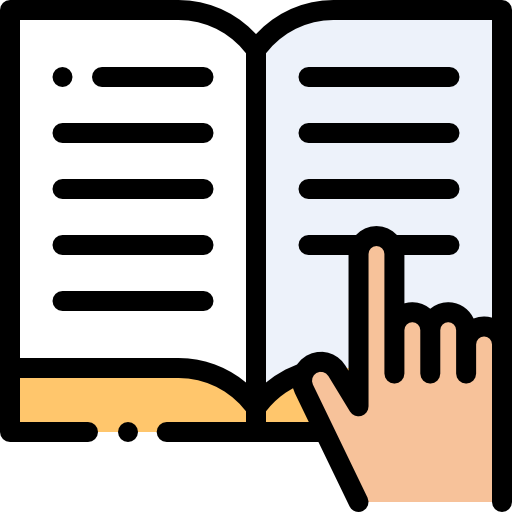
この記事で紹介しているTOEICとは正確には「TOEIC L&R」と言います。
L&Rは「リスニング&リーディング」の略ですので、語学の4技能(聞く、話す、読む、書く)の内の「聞く、読む」の能力を判定するテストです。
実はTOEICには『TOEIC L&R』の他に『TOEIC S&W』というSpeaking(話す)とWriting(書く)の能力を測るテストがあります。
『TOEIC S&W』は2006年に始まったものでそれまではTOEICと言えばL&Rの事であり、「聞く、読む」だけのテストでは不十分との声から開発され、実施されております。
現時点では残念なことにまだまだ浸透しておらず、対策本もL&Rのものと比べても圧倒的に少ない状況です。そういった状況ですので、現時点では一般的にTOEICといえば『TOEIC L&R』の事を指します。
しかし、長年のTOEIC運営の周知活動もあってか、徐々にではありますがS&Wの認知度も上がってきています。
その証拠に企業採用(特に外資系)ではL&Rに加えてS&Wのスコアを求められるケースもあるようですので、これからも様々な対策本が出てくるでしょう。
ビジネスシーンが想定された出題が多い

TOEICで問われる内容は主にオフィスや駅、空港、商店のチラシ等の生活に密着したしたものであり、英検のような社会問題や自然科学、歴史等の教養が求められる話題は取り上げられません。より実務的とも言えるかも知れません。
TOEICの主な受験者層は就職を見据えた大学生や、転職を考えている社会人などですので、英語力がある人材が欲しい企業側にとっては、求職者のTOEICスコアがビジネス英語が出来るかどうかの採用の判断基準となっております。
試験結果は合否ではなく、10点~990点までの5点刻みで評価され、そのスコアは受験後30日以内に手元に届きます。(ネットで受験を申し込んだ場合、それより約1週間早く結果を知ることが出来ます)。
以上のような理由で、TOEICはその用途が比較的明確なのが特徴と言えます。
必ずしも「満点990点=全問正解」と言うわけではない
TOEICの運営母体であるETS(Educational Testing Service)によると、各試験回によってテストの難易度が変わらないようにスコアの算出方法は、スコアの同一化(Equating)という統計処理によって算出されるとのこと・・・。なんか難しいですね(笑)。
でもそんなこと受験者はあまり考える必要はありません。
要するにTOEICは受験者の英語力に変化がない限り、何回受験してもスコアは大きくは変わらないということです。
これはどういうことかと言うと、例えばある特定の問題が受験者全体で正解と不正解に極端な差が生じた場合は「採点自体をしない」ということもあるそうです。
ですので、必ずしも「990点=全問正解」と言う訳ではないと言うことですね。
こうした細かい仕組みによってテストの信頼性が担保されているので、「今回は問題が簡単だったから偶然に高いスコアが出たっ!ラッキー!」のような事は起こりにくいのです。
もし簡単に感じたのならばそれは偶然ではなく、あなたが勉強を頑張った結果、英語力が上がったという証拠です。
繰り返しますが、判定は合否ではなくスコアですので、各自目標とするレベルなりの目標設定をすることが出来ます。
加えて後述する試験回数の多さなども含め、受験者は比較的リラックスしてその時点での自分の学習到達度を確認出来ます。
テキストが多いので対策しやすい
毎年受験者が増えているTOEICですがそれに伴って対策本も豊富にあります。
したがって各出版社、TOEIC講師によって絶えずその傾向と対策も研究されていますので、本人のやる気さえあればいくらでもそれらの対策本で学習が出来るということです。
TOEICを受験しようと思っているのですが”テキストは何を使えばいいのか?”という質問に対してはまずは公式の問題集をやってみることをおすすめしています。
公式問題集をやる際は試験と同様に、ある程度は環境にも気を使って下さい。
出来るだけ静かな環境で時間もストップウォッチ等を使い、最後まで休憩なしで頑張ってみて下さい。
そしてどんな結果でも決して落ち込まないでください(笑)。あくまでもTOEICがどんなものかを知るのが目的です。そこからがスタートです。
スピードが求められる

TOEICの大きな特徴として「解答のスピードが要求される」といったことがあります。
リスニングとリーディングを合わせて200問を2時間で休憩なしで一気に解答しなければなりません。
一つ一つの問題の難易度は高くありませんが、量が多いので大変な集中力が必要となります。
後ろ髪引かれるタイプの人は要注意です(笑)。普段から解答のスピードを意識して問題を取り組むクセを付けておくことが大事です。
特にリスニングの音声は一回流れるだけで後戻り出来ませんので、分からないと思ったら見切りをつけて次の問題に移る潔さが無いと、なし崩し的に次の問題も聴き逃すことになります。
この英語力、集中力に加えて「損切り出来る精神的な強さ」が求められるのもTOEICの特徴です。これも普段から模擬試験で慣れておく必要があります。
時間がないのには意味がある?
個人的にTOEICに関して思うことの一つに、TOEICはビジネスを行う際には欠かせない「タイムマネジメント能力」も重要なスキルと考えているのではないかということです。
ビジネスにおいては目の前にある解決すべき問題の優先事項を瞬時に判断し、処理しなければなりません。
こうした判断力は立派なスキルといっても過言ではないでしょう。
同様にTOEICでも限られた時間の中で分からない問題は切り捨てて、確実に取れる問題を優先させていかなければ制限時間内に全問解答が出来ません。
ビジネスでは時間が掛かろうと目の前の問題と対峙しなければならない時と、後回しにしてもOK(あるいは無視)な問題があります。TOEICは後者のスキルが圧倒的に大事になります。
その時点で自分の能力では解けない問題に囚われるほど無駄なことはありません。適当にマークをして次の問題に全神経を注ぎます。
こうしたことも配慮して問題作成をしているのではないかとふと思うことがあるのですが、考えすぎでしょうか(笑)。
試験の回数が多く試験会場も多い
TOEICは現在、年に10回もの受験機会があります。
受験回数に制限はありませんので、年間10回の公開テストを全て受験することも可能です。
さらに、公開テストの他に企業・学校ごとに実施されるIPテストや大学生協が行うカレッジTOEICも別途受験することができますので、理論的には10回以上受験することも可能です。
一方で英検は基本的には年3回(一次、二次は別日程)ですので、1回の試験に掛かる緊張度も変わってきます。
TOEICの試験会場ですが、全国約80都市で開催されており、受験票を受け取ってから初めて自分の会場が分かるようになっています。
受験者の近辺の大学や専門学校などを運営が郵便番号などを参考に振り分けているようですが、必ずしも希望の会場で受験できる訳ではなく、明らかに近い会場があるにも関わらずに場合によっては乗り継ぎに不便な場所になってしまう時もあります。
一度変更のお願いをしたことがありますが、居住地エリア内での変更は出来ずに、エリア外だとさらに遠方になってしまうために諦めたことがあります。
連続して受験すると同じ会場が続くことが多いようですが、なんとかして欲しい問題でもあります。
個人的には交通が不便な会場よりも音響設備や空調があまり良く無い会場に当たった時の方が絶望感が大きかったです(笑)
しかしハイスコアをコンスタントに取れるようになってからは会場に関してはあまり気にならなくなったのも事実です。それまで様々な経験をしてきた為に多少のことでは動じなくなってきた為だと思います。
連続で受験した方がスコアUPしやすい
TOEICというテストは数年毎に出題のトレンドが変化していく特徴があります。特に近年では2016年に大幅な改訂がありました。
詳しい変更点は他の記事でふれていますのでそちらを読んでいただければと思います。
[blogcard url=”http://t2raw.xsrv.jp/2020/02/16/toeic%e6%94%bb%e7%95%a5%e6%b3%95%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-part-6-%e7%b7%a8%e3%80%8d/”]
しかし”大幅な改訂”といっても基本的な英語の基礎力が問われているのは変わりません。
基本的な学習方法が変わることはありませんが、強いてあげるならばより正確に読むスピードが必要となったということです。
連続受験してわかる変化
実は改訂とまでは言わなくとも、今までも連続して受験していなければ気づかないようなマイナーチェンジは行われてきています
例を挙げれば
・リスニングの話者の国籍が変わる ・ 会話の量が増えることによって難しくなる ・ 文法問題が微妙に難しくなる ・ 長文問題(パート7)での文章量の増加 ・ 同じくパート7において、ヒントとなるキーワードを探し当てれば解答できる問題の減少
などがあります。これらはすべて2016年の改訂以前から少しずつ変わってきたものです。もちろん運営からの告知はされずに「さりげなく変わっていた」ものです。
大幅に改訂されたのが2016年だということです。
もちろん改訂後のこれからも、そうした微妙な変化は起こる可能性は高いです。
TOEICは連続して受験していればスコアが上がるとよく言われます。
それはTOEICの雰囲気に慣れるからという理由もあると思いますが、加えて”受験し続けることでそうした小さな変化に対応することが出来るから”というのもあるかもしれません。
以上となりますがいかがでしたでしょうか?
TOEICの特徴は理解していただけましたででしょうか?
TOEICの各パートにおけるおすすめのテキストや勉強すべきポイントをまとめた記事もありますので、是非よろしくお願いします。
[blogcard url=”http://t2raw.xsrv.jp/2020/02/16/toeic%e6%94%bb%e7%95%a5%e6%b3%95%e3%80%8c%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0part-5%e7%b7%a8%e3%80%8d/”]
